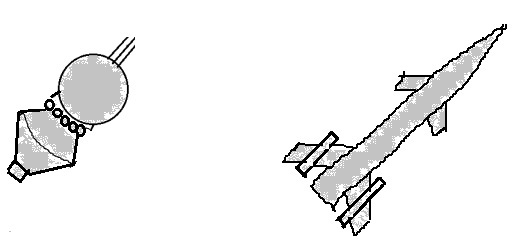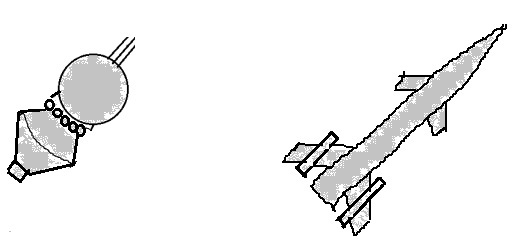ソ連の宇宙開発における隠蔽の歴史 (第1回)
上原 貞治
ソヴィエト連邦の宇宙開発の歴史において、初期の有人宇宙飛行が行われた1961年〜1971年を中心に、どういう事項がどういう理由でソ連で秘密にされたかということを分析したい。私は、これに類した記事として、かつて「銀河鉄道」WWW版第10, 11号に「ソ連の宇宙開発−真実の歴史(
前編・
後編)」を書いたことがある。今回も、それと同様の内容がおもになるが、隠蔽の趣旨について深掘りをしてみたい。
1.初めに〜隠蔽とは何か?
宇宙開発における隠蔽とは何か、というと、宇宙開発を一つの科学技術実験とみた場合、そこで起こった報告すべきことを隠すことである。「秘密にしておくこと」と言ってもいい。意図的に公表をしなければ隠蔽なり秘密には違いないが、技術開発において先端技術に絡むことは、公表に慎重になるのは当たり前で、公表しないから隠蔽だ秘密だと揶揄するのはおかしい場合も多い。まず、国防能力に関することは通常機密で、どこの国でも当然に秘密である。また、民生品メーカーでも、特許を意図した場合は、請願までは秘密である。これらは、当時の宇宙開発に特化した事情とは言えない。
「共産主義だから秘密主義」というのも、ステレオタイプである。むしろ、上の事情では、資本主義が機能し開発競争が激しいほど、技術の秘密は増えるはずである。共産主義のほうが、国家が産業を率いていて、プロパガンダとして宣伝するのが当然なくらいである。だから、ソ連の宇宙開発での隠蔽を、軽々に共産主義と結びつけるのは正しくない。ここには、国際競争の視点が加わる。当時で言えば、ソ連がアメリカに負けていて、ひそかに追いつこうとしていたなら隠したい実態もあったかもしれない。しかし、彼らはむしろ勝っていたのであるし、勝っていた分野も隠していた。一般には、勝っている分野を秘密にするのは、優位を維持する意味からとなるが、当時は、たとえアメリカに漏れたところで簡単に追いつかれるような事情にはなかった。ソ連が実際に秘密にした理由については、個別に内容の性格を検討をする必要がある。
2.人工衛星スプートニク
基本的に、ソ連の初期の宇宙ロケットは、もともと弾道ミサイルとして開発されたものを宇宙用に応用したものである。それは、当時の世界常識で、アメリカにおいても、アポロを打ち上げたサターンロケットより前のロケットはすべてミサイルの転用と言ってよい。1960年代以前では、サターンロケットだけが有人月飛行という非軍事目的のために開発されたものである。この常識が通用したのは1970年ごろまでであって、サターンの成功後は、軍事用と宇宙用は別々に特化させてロケットを開発するほうが効率的であることがわかり、これは今日の常識ではない。
ソ連の1950年代の人工衛星スプートニクに至るロケット開発が軍事主導であったことは本質的である。ソ連は第二次大戦中にロケットの独自開発をしていたが、大戦終了時にドイツから拉致してきた技術者をミサイル開発に従事させた。それ以降、ソ連のロケットの原点は、ドイツの液体ロケットミサイルのV2号である。ソ連は、V2号のデッドコピーを初めとして、R-1,R-2.、R-3・・・と呼ばれる弾道ミサイルの開発を進め、途中からソ連独自の設計も含め、アメリカ大陸まで届く大陸間弾道弾(ICBM)を作ろうとした。そうして、R-6で一応のロケットとしての完成を見たのである。ところが、ここからが難題だった。
十分な重量の爆弾を載せて遠くアメリカ大陸まで飛ばすためには、R-6を多段式にすればよい。それは以前から知られていたアイデアである。それにより、上段の重量が増すので、ロケット(この場合はR-6を基に改良した液体燃料ブースター)を複数本束ねる「多列式」(クラスターロケット)のアイデアが考えられる。戦前からソ連のミサイル開発を担当していたコロリョフもこれを考えた。これは誰でも思いつくアイデアだが、実現が難しいこともすぐにわかる。束ねたロケットが正確に同じ性能でなければ、まっすぐ飛ばないことは明瞭である。コロリョフが優れていたのは、この多列式ロケットを実現できたことである。
R-7の一段目は、ロケット1本を中央に、周囲に4本、計5本を多列に組んで、周囲の4本をブースターとして、上昇中に、ロケット全体の進行方向を自動的に機械制御する機構のものであった。中央の1本は、周囲の4本が切り離された後も飛翔を続ける1.5段式と呼ばれる方式である。ここから、R-7のICBMとしての開発が始まった。ところが、上昇はうまく行ったが、弾頭部分の大気圏再突入で手こずった。大気圏再突入で、弾頭が損傷したり、方向が十分に制御されないことがあった。
そこで生まれたのが、大気圏再突入を必要としない、人工衛星、スプートニクの計画である。これには、R-7の上にロケットをもう1本足して、宇宙空間で点火し、地面とほぼ平行に地球周回速度の8km/毎秒まで加速すれば、人工衛星を軌道に乗せられるものであった。こうして、スプートニク1号は、人類初の人工衛星として軌道に乗った。スプートニクの衛星部分は、その形状が公表され、電波の発信も公開された。しかし、打ち上げロケットは完全な秘密であった。下部の1.5段のR-7は、ICBMとしての開発途上のものだからこれは当然である。次のスプートニク2号は、犬を乗せて打ち上げられたが、これも同様に人工衛星部分は形状が公開された。この犬には気の毒にも回収計画がなかったので、大気圏突入の装備がなかったため、ICBMとの関係が問題にならなかったためと見られる。その後の1959年までのスプートニク3号、月探査機のルナ1号(月を逸れ人工惑星になった)、衝突した2号、月の裏側の写真を撮った3号は、いずれも、衛星、探査機の形状が公開された。打ち上げロケットは、どれもスプートニクロケットの派生形で、R-7の上段に宇宙空間での加速、減速用のロケットを追加したものであった。つまり、ロケットは秘密で、宇宙に出て帰ってこない部分のみが公表された。
3.有人衛星船ヴォストーク
この状況は、1960年以降のコラブリ・スプートニクから、がらりと変わった。人工衛星の形状も公表されなくなったのである。スプートニク4号(コラブリ・スプートニク1号)を祝する記念切手のイラストでは、漫画にでてくるようなロケット型の衛星が描かれた(図1右)が、これは現物(図1左)とは似ても似つかないウソであった。これは、コラブリ・スプートニク(このロシア語は、「宇宙船・衛星」の意味)が人間が搭乗するための宇宙船の試験機で、後のヴォストーク宇宙船に繋がるものであったためである。宇宙船は、回収可能でないといけないので、開発が進むと大気圏再突入用のエンジンや熱シールドが装備された。これらの装備は、同時期のR-7型ICBMの弾頭実装として開発されていたものと関連付けられるので、秘密とされたと見られるが、実は、それだけではなかったらしい。コラブリ・スプートニクやヴォストークの記念切手にある虚偽の描写を見ると、初の人間の宇宙飛行に使わせる宇宙船は、昭和期の漫画に出てくるような流線型のロケット型をしている。これは、できることなら、人間が乗る宇宙船は、カプセル型のパッシブな飛行体ではなく、人が自在に操縦するミグ戦闘機か、あるいは、後のアメリカのX-15や人形劇のサンダーバード1号みたいな飛翔体であってほしかったのではないか。
図1:(左)コラブリ・スプートニク1号(ヴォストーク1K型宇宙船)
(右)スプートニク4号としてソ連の記念切手に描かれたイラスト
(いずれも、ネット画像からの筆者(上原)による適当模写)
ところが、実際に、1961年にユーリ・ガガーリンが搭乗したヴォストーク1号の船体は、犬の乗ったスプートニク2号と同様に、球体カプセルであった。この球体を人間が操縦することもほとんどなかった。自動飛行する設計だったからである。実際、ヴォストークに先立つコラブリ・スプートニクのテストでは、2匹の犬が飛行して、無事地上に帰還している。犬の帰還は誇らしげに世界に公表された。でも、これは矛盾をはらむ。何も操縦をするはずのない犬が帰還できる宇宙船であるのに、次に飛行するガガーリンは特筆すべき国家の英雄であってほしかったのである。犬の乗ったコラブリ・スプートニクとガガーリンが乗ったヴォストークの船体形状は、基本的に同じであったが、ともに完全な秘密とされた。球形のカプセルというのは、熱的にも圧力的にもシンプルで優れた設計で、だからこそ自動運転で早期の宇宙飛行が可能になったのだが、その全体が隠蔽された。
しかし、それにも関わらず、ヴォストークのガガーリンやテレシコワは、紛れもなくソ連の国家的英雄になった。それは、彼らが世界を回り、世界中で彼らの勇敢で知的で常識のある親しみやすい人柄が歓迎されたからである。宇宙船もロケットも秘密であったが、宇宙飛行士の個性は最大限に宣伝された。
実際には、さらにもう一つの問題があった。それは、彼らの地上帰還方法に関する問題である。実際には、ガガーリンは、ヴォストークの船内に留まったまま、ロシア南西部に着陸したわけではない。射出座席という、非常時にパイロットが軍用機から座席ごと脱出するような装備で、パラシュートで帰還したのである。ヴォストーク本体も別のパラシュートで減速して回収されたが、飛行士が乗ったままでは安全が保証されないものだったので、脱出が既定であった。ところが、当時の宇宙飛行ルールでは、人間が宇宙に行って帰ってきた認定として、宇宙船に乗ったまま帰還することが求められていたので、この脱出の事実は隠蔽された。ガガーリンは、1968年に訓練中の事故で死亡したが、それまで着陸の最後の瞬間については多くを語らず、宇宙船から独力で外に出たことしか述べていない。また、ヴォストークには、緊急脱出装置とパラシュートと逆噴射機能が装備されていて、これらを飛行士の判断で選んで利用できたと説明されたことがある。最初の2つは装備があったが、最後の逆噴射装置は存在しなかった。非常脱出装置は、コラブリ・スプートニクの犬の例でわかるように、高度計に連結して自動的に動作するようになっていた。この真実は、1970年代にテレシコワが明かすまで秘密にされた。彼女はパラシュートをつけたまま木に引っかかって、顔に怪我をしたという。しかし、これが一般に知られた時には、すでに、これは、父が戦死し母が紡績工であった英雄テレシコワの庶民性に貢献するエピソードになっていたはずである。
4.ヴォスホートから1965年まで
ソ連のヴォストークによる有人飛行は、世界に大きな衝撃を与えた。これをきっかけに、アメリカのケネディ大統領は、アメリカが1960年代に有人月着陸を達成することを宣言した。これに対抗して、ソ連もアメリカに先駆けた有人月着陸を計画したが、それが公表されることはなかった。もとよりソ連も月飛行を考えていなかったわけではないし、ソ連の現状は、アメリカより先を走っていたので、公表してわざわざ対抗するメリットなかったものと説明できる。
月着陸に必要な開発事項として、複数人が搭乗する宇宙船の打ち上げと船外活動がある。これらは、ヴォストークに続くヴォスホート計画で1965年までに達成された。ヴォスホートは、ヴォストーク同様球形のカプセルだったが、ヴォスホート2号には、宇宙遊泳のための船外に出るためのシュート状の気密空間が付いていた。しかし、この形状もすべて秘密とされた。レオーノフ飛行士による世界初の宇宙遊泳の成功は、宇宙空間に浮かぶ飛行士の部分のみの写真が公表された。ヴォスホート2号の特殊な構造はその場限りのもので、後に生かされることはなかった。ヴォスホートの打ち上げロケットについては、R-7の上段増強型であり、基本的構造は従来型で、これまでと同様秘密にされた。
いくつかの変化があった。1964年10月、ヴォスホート1号の飛行中に、ソ連共産党のトップであったフルシチョフが失脚した。フルシチョフは、宇宙計画を成功裏に進めることでソ連の科学技術上の地位を築いた人であり、失脚の時も計画は順調であった。フルシチョフと後継のブレジネフは対立していたが、フルシチョフは明朗闊達な気質を持ち、ブレジネフはそれよりも地味で穏健な人であったので、失脚によって、隠蔽政策が進むということはあったかもしれないが、大きな変化はなかった。
それでも、ブレジネフは、1965年から、少しずつ過去の開示を始めている。以下、本連載では、筆者(上原)は、当時の日本の月刊科学雑誌『科学朝日』(朝日新聞社)を見て、ソ連の宇宙開発の公開報道をピックアップする。アメリカの月刊科学雑誌Scientific American(後にこれの日本版が『日経サイエンス』となる)も見たが、当時のアメリカの雑誌は、ソ連の成果をわざと毛嫌いして載せていないように見え、あまり役に立たない。悔しかった側だから当然だろう。ソ連の報道に関心が深いのはむしろ日本である。
それによると、1965年の対独勝利20年の軍事パレードやモスクワの経済発展博覧会で、R-6ミサイル単体とヴォストーク宇宙船が公開されている。ヴォストークが球形のカプセルを持つことが、写真で世界に配信された。これは、R-7がアメリカ本土に届くICBMとしてはあまり実用的でないことがわかったこと、それから、アメリカでも、ミサイルの上段にマーキュリー宇宙船やジェミニ宇宙船が搭載された事情が世に知られたからではないか。マーキュリー宇宙船の円錐状の多少しゃれた形はしているが、狭っ苦しいカプセルであることに変わりはなく、そうであれば、世界初であるヴォストークのほうに宣伝の価値がある。しかし、この時点では、R-7派生型の打ち上げロケットの形状はまだ公開されていない。
しかし、その後、ソ連の有人月計画は、複雑な事情の積み重ねにより混迷を深めていく。月着陸計画には、月着陸船と母船(地上へ帰還する宇宙船)の両方が必要になり、それらのドッキングや移乗の技術が必要である。それは、ヴォスホートでは実験できず、次世代のソユーズ宇宙船計画に持ち越された。そして、ソユーズ計画は、月飛行計画というその全体目的を隠蔽しつつ、途中の成功の部分だけは外に公表されるようになったので、外からは、謎の計画が進められているように見えることになった。さらに、内部での計画の困難や混乱がそれに拍車をかけることになった。
5.ソ連の宇宙計画隠蔽の基本的な考え方
このあとは、ソ連が極秘裏に進めた有人月飛行計画ソユーズの複雑な内容がメインになるので、そのまえに、今回の最後で、ソ連の宇宙計画の隠蔽の普遍的かつ基本的な考え方をまとめておきたい。
まず、ソ連では、軍事装備に関することは秘密である。装備の図面や性能が秘密にされるのはどこの国でも当たり前のことであるが、ソ連では、映像や略図に属するものまで、いわば存在のすべての秘密が基本である。この連載で出てくるソ連の主要な打ち上げロケットは、R-7の派生型ロケット(スプートニク、ヴォストーク、ヴォスホート、ソユーズのそれぞれの打ち上げ用)とプロトンロケットとN-1 ロケット(さらに大型のロケットで次回に出る)しかないが、最初の2つはともに軍事アイテムであったので、秘密にされた。しかし、時間が経った後は、例外的に公開されることはありえた。他国の例だが、近年は、北朝鮮がミサイル発射の映像を公開したり、軍事パレードでトレーラーに乗せて引き回している。こういうのは、北朝鮮のミサイル用ロケットが世界水準から見て時代遅れだからできることで、世界の最先端を走る兵器ならそういうことはしないのが普通である。N-1 ロケットは、月飛行用のロケットで軍事用ではないが、有人月飛行計画自体が全面的に秘密なのでともに秘密にされた。
次に、ソ連は、失敗を隠蔽した。失敗を成功と偽ることはほとんどなかったが、失敗を告白するようなことはなかった。しかし、これもソ連に特有のことではなく、今日の資本主義国の民間企業でもすべての失敗を公表して自らのメンツを潰したり、株を下げるようなことはしない。ところが、宇宙開発には、特有の国際的な約束があって、「飛翔体が宇宙空間で何らかの軌道に乗った場合」「飛翔体に人間が乗っていた場合」は、成功、失敗に関わらず、報告をすることになっていて、何もなかったことにはできないのがルールである。ソ連は、共産主義国として世界の指導的立場に立つ建前なので、国際標準に従わざるを得ない。無人の飛翔体でも軌道に乗ったら、たとえ失敗の部分が多くても、成功部分を強調する形で公表がなされた。当たり障りのない範囲でウソがはいることがあった。人工衛星が軌道に乗ったものの通信が途絶えて何の試験もできなかった場合にも、「軌道に乗せ、科学的観測を行い、技術的データの収集を行った」のような発表をした。意味のあるデータがまったく得られないこともあったのでこれはウソとも言えるが、地上からモニタをしたのは事実なので、許される範囲のウソということであろう。
有人の場合は、宇宙飛行士の名誉がかかっているので、もう少し、真実に近い発表がされた。計画のうまく行ったところまでが強調され、飛行士が帰還できた場合は、「無事帰還した」と報告され、不幸にして飛行士の生命が失われた場合は(次回以降、述べるように、それは2度しかなかったが)、その事情がただちに報告され、国家英雄として国葬が行われた。
ソ連の世界初の人工衛星と有人飛行は、OKB-1設計局(設計局の多くは元々は軍事開発である)のリーダーのセルゲイ・コロリョフの優れたアイデアと指導力によるものであった。しかし、彼の名前は国内にも公表されず、別の事情を何も知らない人物が代表者として紹介されていたという。ノーベル賞委員会が、人工衛星の功績を授賞候補にと考えて、ソ連政府にリーダーの名前を尋ねたことがあったが、政府は「スプートニクの成功はソ連人民全体の成果である」と答えて、コロリョフの名前は出さなかったという。いかにも共産主義国らしい答えではあるが、実際には、ソ連科学アカデミーの学者でノーベル賞を受賞した人はいるし、科学アカデミーも個人を表彰をしている。コロリョフの師匠である航空機設計者のツポレフの名は、軍用でも民用でも世界的によく知られていたし、すでに述べたように、ガガーリンもテレシコワも国家英雄になった。コロリョフは、何から何まで隠蔽され、ロケット開発をしていたのでやむを得ないとは理解しただろうが、さすがにノーベル賞の時は落胆した様子だったと言われている。また、本当は、コロリョフの名を積極的に伏せる必要はなかったのだが、彼の暗殺や誘拐を避ける必要からそうしたという説もある。それを裏付けるかのように、1966年の没後は、ただちに名前が公表され、国葬が行われてクレムリンの壁に埋葬された。
ソ連の宇宙開発では、事前に計画が予告されることはなく、ただ成功の部分のみ公表されたので、部分的な成功の場合は、尻切れトンボの何がしたかったのかわからないような発表になることが多かった。それを解くのが「西側アナリスト」の楽しみであったのだが、これはソ連国民にとっても同様だったのではないか。未公表部分の中身については、失敗とみるのも良し、詳細の詮索も良し、次回以降の成功の時のお楽しみでも良し、失敗が続くとそれが小出しに出てくることになった。
次回は、その全体目的が隠蔽されたソ連の有人月計画について、具体的な内容をみてみたい。
(つづく)
今号表紙に戻る