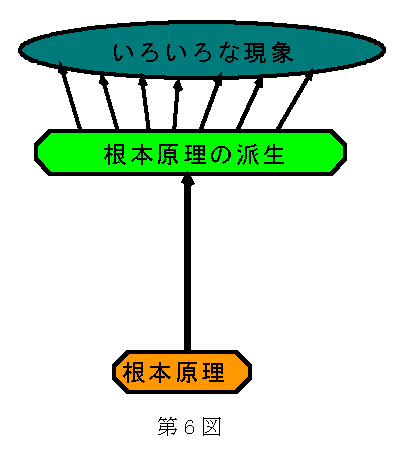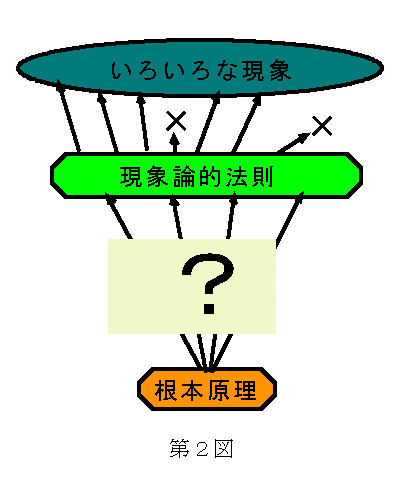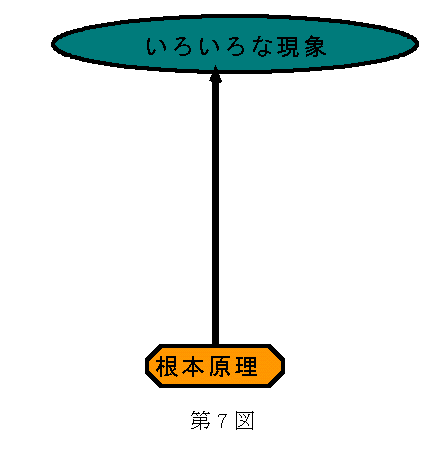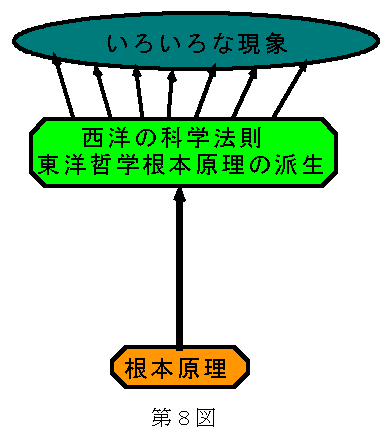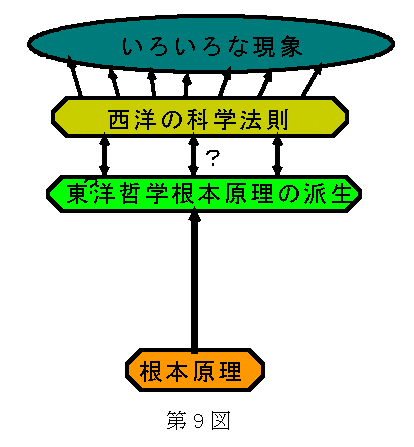西洋の科学、東洋の科学と日本の科学(第3回)
上原 貞治
7.江戸時代の儒学者
前回取り上げた江戸時代の暦学者は、天体の運行を予言する計算方法を改良する能力を持っている極めて限られた特殊な人々でした。では、一般の知識人はどうだったのでしょうか。(一般の知識人というのは妙な言い方ですが、江戸時代には士農工商の身分を問わず、学問に熱心な人は全国にあまたいたのです) ひとことで言うと、ほとんどの知識人は、儒学あるいは朱子学を思想の根本となる学問と考えておりました。仏教や神道の関係者は当然異なる思想を持っていたでしょうが、ここでは触れません。
朱子学は、中国の儒学を南宋の時代に再整備したもので、それは自然哲学から倫理、社会の分野まで幅広い内容を含むものでしたが、封建社会での秩序の維持と教義が一致したため、幕府によって後に官学とされました。朱子学の自然哲学は、古代中国の思想である「気」をおおもととし、これに「易」の「陰陽」それに「五行説」を組み合わせ、これをもって自然界(人体を含む)の万物を説明しようとします。朱子学において重要なことは、「理」です。自然界のものは、おのおのの「理」によって秩序正しく成り立っていると見たのです。現代の言葉で説明しますと、「気」は元素のガス体のようなもの(連続体であって粒子ではありません)、「陰陽」は「気」の「暗い状態」と「明るい状態」の2通りの状態、「五行説」は陰陽の気が凝縮してできた5つの元素(木・火・土・金・水)、「理」は自然の摂理あるいは法則、ということになるでしょうか。「易」とか「陰陽」とか言いますと、占いか呪術師のようなものを思い浮かべられるかもしれませんが、もともとの自然哲学にはそのような非科学的なニュアンスはありません。のちの時代に「陰陽」を占いや呪術に利用しようとした人々がもてはやされた時代があった、というだけのことです。
これを図で示すと第6図のようになります。根本原理は、気と陰陽による自然哲学の原理、そして「根本原理の派生」とはこれからじかに導き出される五行説や「理」の適用を指します。これらが実際の現象にごく近いところに設定されている(図では上寄りに書かれている)ことが特徴的です。東洋の自然哲学では、根本原理から派生したものが素直に現象にごく近いところまで接近しているのです。たとえば、気候や雷のような気象現象は、いきなり陰陽の気によってダイレクトに説明されました。 西洋の近代科学では、分子説や熱力学や電磁気学を必要とするところですがこのような「中間的な科学原理」は、東洋では一切必要とされなかったのです。そして、この「派生」と現象をつなぐものが朱子学で言うところの「理」なのですが、これはこのままでは科学と言えるものではありません。自然界で起こっている様々な現象をそれぞれ「理にかなっている」というだけなら、これはただの批評あるいは結果論的説明であり、いかなる法則も引き出すこともできなければ、新たな技術的応用を発見することもできないからです。それを可能にするには、別の方法(第1回に出た第2図、下に再掲)によらねばなりませんでした。つまり、第6図が「タテマエ」で第2図が「ホンネ」だったのです。
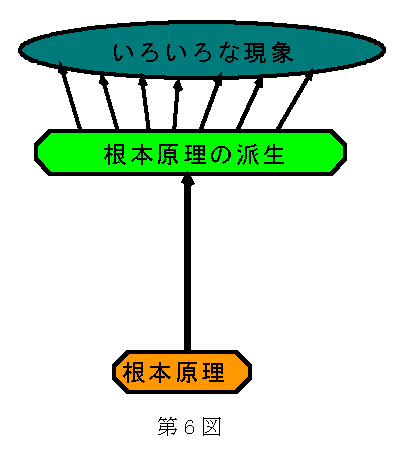
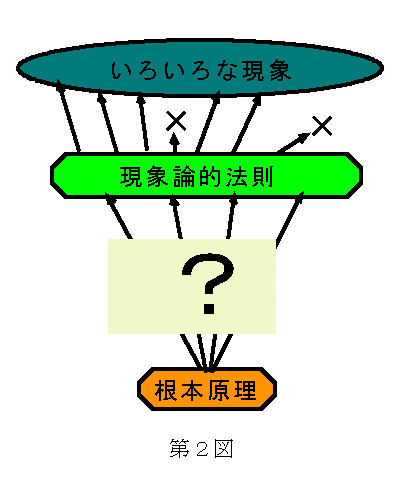
今度は東洋医学を例にとりましょう。東洋医学では、人体の内部には陰陽の気が流れており人体に含まれる五行の元素がそれぞれの機能を果たしている、と考えます。これのバランスが失われた状態が「病気」です。ですから、病気を治すにはその人の身体全体の陰陽五行の様子を把握してバランスを回復する策を講じないといけません。ここまでが「タテマエ」です。しかし、易や朱子学をいくら究めたところで科学的に有効な治療手段が見つかるとは思えません。では、なぜ、鍼灸や漢方薬は現実に治療に効果があるのでしょうか?それは、第2図です。中国四千年の歴史の経験と研究から、病気の治療に有効な技術が現象論的に集積されて来たのです。医学の威厳を守るためには「タテマエ」が必要ですが、「ホンネ」としては、陰陽五行はどうであれ、医学は病気を治してくれればそれでよいのです。
「タテマエ」と「ホンネ」の両方を尊重することは、日本人が古くから得意とするところでした。しかしながら、このような態度は、真摯に真理を追求しようとする進歩的な学者の納得するところではありませんでした。
8.自然哲学の再構築・三浦梅園
豊後の国の三浦梅園(1723-1789)は、このような朱子学の自然哲学を真理と考えることができませんでした。それで、すべてのことを疑うことから始め、自然哲学の再構築を行いました。梅園は、古代中国の自然哲学の根本原理の再定義をするところまで遡りました。彼にこのようなことができたのは、彼が、あらゆる先入観を捨て世界をただ見たままに理解すること、複数の対立・並立する自然現象の中に真実を探すという方法を採ったからです。そのような意味において、梅園は、西洋的かつ近代的な研究手法をとったのですが、これは西洋の科学や自然哲学の影響を受けたものではなく、彼が独自に切り開いた方法でした。彼は暦学者・麻田剛立や長崎のオランダの関係者などから西洋の自然科学を学びましたが、それは最新の天文学研究の成果を知るためであり、西洋の哲学や研究手法を学ぶことはありませんでした。梅園は、日本史の中で栄光の孤立を守っている傑出した哲学者ということができます。
梅園が到達した自然哲学の根本原理は「気」の一元論と「陰陽」による展開でした。梅園の「気」の一元論は、中国の古代の自然哲学のそれ(太極)に近いものでしたが、「陰陽」はもっと無機質的なもので、数学的なプラス・マイナス(電磁気学の電荷のような)概念でした(梅園は、この再定義を明確にするため、「陰」「陽」から「こざとへん」をとった独特の漢字を使っていますが、その「いん」の字がJIS漢字にないのでここでは「陰陽」と書くことにします。なぜか「昜」はあります)。彼は、五行説はとりませんでした。理論に無駄な前提を起きたくない彼にしてみれば五行説は不合理なこじつけに過ぎませんでした。
さて、梅園の自然哲学の神髄は、「陰陽」を無限(有限かもしれないがかなりの多数の)の階層に分けたことにあります。つまり、自然(人体や天体も含む)のものや現象のすべてを「陰陽」の組み合わせで説明したのです。陰陽を数学記号としての「プラス・マイナス」と見れば、これは一種の「2進分類」と呼ぶことができるでしょう。彼は、これによって、根本原理を諸現象まで一気に結びつけることができたのです(第7図)。このような途方もないことを可能ならしめたのは、彼の理論が階層の異なるすべてのレベルに対称性を要求したことによります。この対称性は、丁度、宇宙→素粒子の異なるレベルにおいて、銀河、星、太陽系、惑星、衛星、物質、分子、原子、原子核、陽子、クォーク、・・・・と多くの(しかも似たような構造を持つ)階層があることを思い起こさせます。また、現代数学で言うところの「フラクタル」(相似的な同じ形が無限の階層において現れる図形)のようなものも想像させます。つまり、梅園の自然哲学は「数学的なモデル」であったと言うことができます。
梅園は、この対称的な法則を「条理」と呼びました。そして、この条理を諸現象に適合させ、それから別の現象間にもその条理を適用しようとしました。梅園は、理論からの予想を現象で証明するという帰納と演繹の双方を用いた東洋哲学には希有な方法で自己の学問を進めました。
このように梅園の自然哲学は時代を先取りしたものでしたが、彼が完成させた自然哲学は事物の分類という「静的な思考」に留まり、複数の諸現象の関わり合いというダイナミックスを含むものではありませんでした。また、彼は定量的な測定や計算をしたり、自然現象に予言を与える「科学者」でもありませんでした。ここに彼の自然哲学の限界があったことも忘れてはなりません。彼の太陽系宇宙論には、ダイナミズム的な見方の萌芽が見られます。超自然的な仮定をおかずにこれを発展させるためには、ニュートンの科学のように数学的な力学理論をたてる必要がぜひあったのですが、彼にはそこまでの知識も能力もなかったのです。それ故に、彼の自然哲学は物理学にはなりえませんでした。
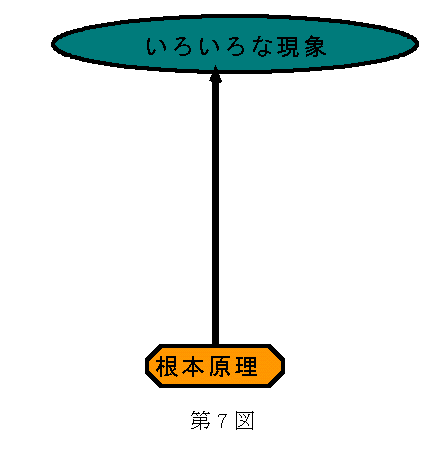
9.東洋哲学と洋学との接続
18世紀の後半から19世紀の前半の江戸時代において、蘭学がさかんとなりました。そして後にそれは洋学となりました。蘭学と洋学はどう違うか、というと明確な違いはないのですが、個々人がオランダの書物を読んでいる段階が「蘭学」、そのような蘭学者が複数いて一定の主張を持った学派が形成された状態が「洋学」ということになるのでしょうか。
さて、江戸時代に「洋学」派がいれば、それは「東洋哲学派」すなわち「儒学・朱子学派」と対立するはずです。確かに多くの場合そうだったのですが、そうでない場合、すなわち、儒学者が儒学を信奉したまま洋学を採り入れた場合もあったのです。世にも不思議なことが起こったと言えましょう。
志筑忠雄(しづき ただお)(1760-1806)は、長崎のオランダ語通辞でしたが、自然科学の資質に恵まれ、オランダの科学書の読解をしました。そして、翻案書(漢文での訳と日本で語の解説を付けている)を出しました。彼が、分子間力(まだ仮説の段階)、地動説、ニュートン力学、といった西洋の科学を理解する際には、東洋哲学を土台としました。つまり、根本原理は中国古代の自然哲学とし、現象論的法則→諸現象の部分は西洋の近代科学(おもにニュートン流の科学)を借用し、全体を構成したのです(第8図)。まさに木に竹をついだのです。でも、考えてみますと、これは自然な成り行きだったかもしれません。志筑にとっては、ニュートンの科学は斬新なアイデアであり、実地の自然現象の理解を画期的に助けるものであったと同時に、根本原理に触れないもの足りないものであったと思われます。しかし、当時の西洋科学の根本的原理はキリスト教だったのかもしれず、キリスト教はもちろん日本では御法度でした(だから、蘭書に書いてあっても翻訳することは出来なかった)から、これは好都合な状況であったといえます。また、東洋哲学は、原理と理においては深みがあるものでしたが、実地には役に立たないものでした。この両者がお互いに補うようなシステムを作ることは、頭の柔らかいオランダ語通辞に最適の仕事だったと思われます。これには、彼がニュートン流の「より根元的な原理」を理解できたことが大きかったと思います。
もう一人の傑出した学者、帆足万里(ほあし ばんり)(1778-1852)を紹介しましょう。彼は、豊後の人で同郷の三浦梅園の唯一の後継者といわれている人です。彼の名前は軽妙洒脱なペンネームのように聞こえますが、実際には藩の家老までつとめ儒学をまじめに学んだ人でした。しかし、彼には他の儒学者と違ったところがありました。彼はオランダ語の科学書が読めたのです。
帆足が三浦梅園の自然哲学理論をどこまで理解しそれに同意していたかは定かではありませんが、梅園のいう「条理」が自然の理解にもっとも重要であることを十分認識していたと思います。ですから、彼の根本原理は梅園のそれ(第7図)に近いものであったと思われます。一方、彼は志筑同様、蘭書から西洋科学の現象論的法則を採り入れることができました。
帆足において特筆的なことは、彼が「東洋哲学の派生」と西洋科学の「より根元的な原理(西洋科学の法則)」の整合性にまで立ち入って議論したことです。彼は主著「窮理通」で、様々な自然現象に対する西洋科学の立場からの説明の後で、自分自身の考えを添えています。例えば、西洋の科学の原理では重力と磁力とは別種の力ですが、帆足はこれらは同一起源の力であると考えました。彼の自然哲学の原理は、「一元気」の根本原理に直結していますので、自然界にある引力は同一起源でなくてはならかなったのです。帆足の反論は科学上はほとんどの場合誤りであり、彼の知識の不足に起因しています。しかし、より重要なことは、 帆足が、いたずらに西洋の科学を排斥することもなく、また鵜呑みにすることもなく、冷静にその間の相違点・問題点を指摘したことです。(第9図)
19世紀前半に、江戸時代の多くの知識人は、日本語で書かれた多くの啓蒙書によって、蘭学の成果に触れることができるようになりました。そして、儒学・朱子学の自然哲学を信じたまま、西洋科学の新奇で合理的な成果を採り入れるようになりました。地動説にとまどうことはありませんでした。月から地球を見ると、月が地球になり地球が月に見えることもすんなり理解できました。他の天体に宇宙人がいると断言した書物を出しても発禁になることもありませんでした。「タテマエ」と「ホンネ」はうまく共存できたのです。
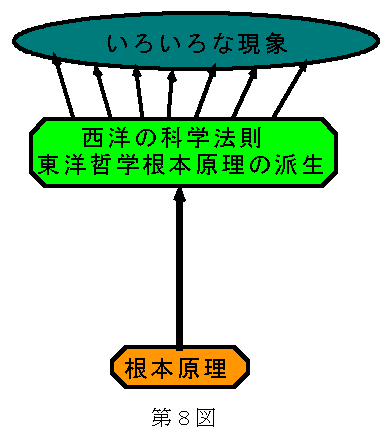
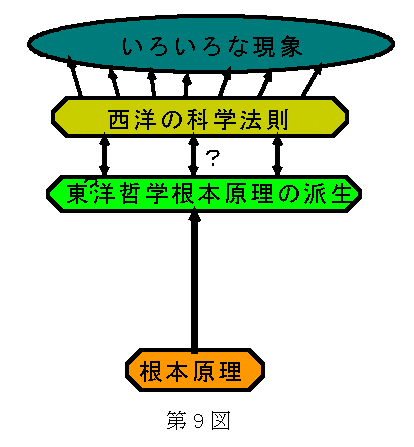
私には、これが「和魂洋才」という言葉に象徴される「日本の科学の合理主義」というものだったのだと思われます。表題にある『日本の科学』とは何ぞや、と聞かれると私は答えに窮せざるをえません。しかし、高橋至時、三浦梅園、志筑忠雄、帆足万里と言った人々を思い出すと、「彼らが切り開いたものは確かに『日本の科学』と言えるものであった」ということが確信できるのです。
しかし、時代は移っていきました。開国し西洋に追いつくためには、木に竹をつぐだけではだめだということに日本のリーダー達は気がついたのです。そして、東洋流の自然哲学と洋学は対立し、前者は排斥され、後者の導入一辺倒となったのです。これは、明治以降、産業技術や軍備を近代化するために正しい選択であったことは認めざるをえません。西洋流の産業革命は、何よりも社会全体を統一する構造やシステムの上に立脚することを必要とするものだからです。
こうして、志筑や帆足の「日本の科学の合理主義」は忘れ去られました。しかし、忘れ去られたものが必ずしも無駄なものではない、ということは歴史が証明していることです。彼らの仕事の意味は20世紀になって再発見されることとなるのです。
次回は最終回として、現代の素粒子・宇宙物理学を取り上げたいと思います。
江戸時代の天文学、自然科学、自然哲学についての入手可能な参考文献はそう多くないと思いますので、いくつかを以下に列挙しておきます。
参考文献
「日本の天文学」、中山茂、岩波新書、1972
「明治前日本天文学史」、日本学士院編、日本学術振興会、1960
「近世日本天文学史」(全2巻)、渡部敏夫、恒星社
「日本科学史の射程」、伊藤俊太郎、村上陽一郎編、講座 科学史4、培風館、1989
「宇宙に取り憑かれた男たち」、的川泰宣、講談社+α新書、2000
「近世日本科学史と麻田剛立」、渡辺敏夫、雄山閣、1983
「麻田剛立」、末中哲夫、他、大分県先哲叢書、大分県教育委員会、2000
「麻田剛立資料集」、大分県先哲叢書、大分県教育委員会、1999
「三浦梅園自然哲学論集」、尾形純夫、島田虔次、岩波文庫、1998
「三浦梅園」、日本の名著、中央公論社、1982
「三浦梅園」、日本思想体系、岩波書店、1982
「洋学 下」、日本思想体系、岩波書店、1972
"Newton in Japan"、 S.L.Montgomery、 Nature 411巻25頁、 2001
「帆足万里の世界」、狭間久、大分合同新聞社、1993
「増補 帆足萬里全集」、ぺりかん社
「富永仲基、山片蟠桃」、日本思想体系、岩波書店、1973
「遠鏡図説・三才窺管・写真鏡図説」、江戸科学古典叢書38、恒和出版、1983