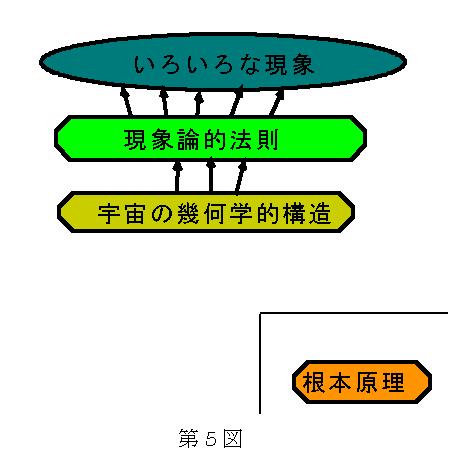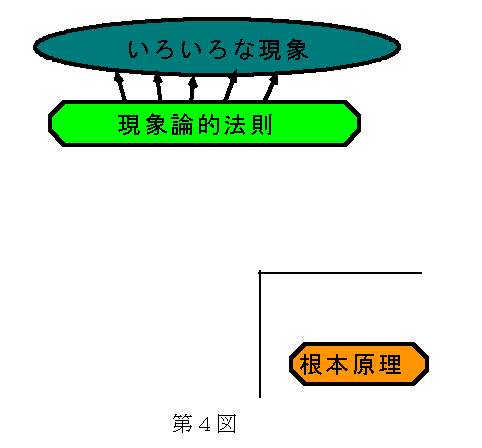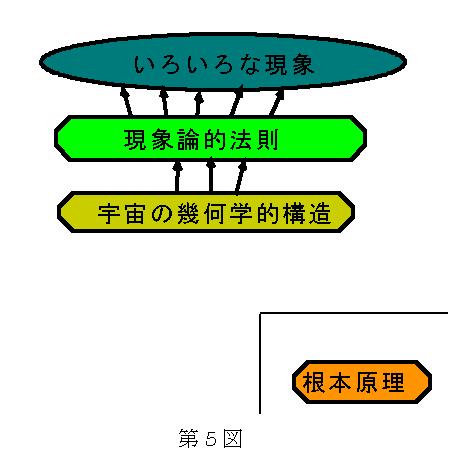西洋の科学、東洋の科学と日本の科学(第2回)
上原 貞治
4.江戸時代の自然哲学、自然科学
さて、いよいよ日本の江戸時代について書きます。まず、江戸時代の自然哲学と自然科学の概況について説明しておきましょう。
江戸時代は、1603年から1867年までということになっていますが、この間にヨーロッパの近代科学は怒濤の進歩を遂げました。日本は、江戸時代の直前と幕末に直接西洋と接する機会を持ちましたが、江戸時代のかなり長い期間は鎖国下にあったので、西洋との接触は限られたものでした。
江戸時代の日本の自然哲学は、古代中国の儒学の流れを引き、宋代に朱熹によって完成させられた朱子学を基礎とするものでした。朱子学は、自然哲学と人間社会における倫理学を一体にしたところに特徴があります。自然哲学としては、古代中国以来の「気」を「陰陽」の二元によって展開し、これによって森羅万象を説明しようというものでした。そして、これを倫理・社会にも敷衍し、個人や人間社会の理と秩序を維持することを説いたのです。
江戸時代の直前には、ポルトガル人やスペイン人の宣教師によりキリスト教が布教されましたが、彼らはとくにヨーロッパの近代的合理思想を広めることはありませんでした。日本に来ていた宣教師は、その対局に位置する原理主義(復古主義)的な人々でしたので、日本の自然哲学に大きな影響を与えることはなかったのです。しかも、まだ西洋の近代科学は開花しておらず(1603年は、西洋では、ガリレイやケプラーが、研究を開始した時代にあたります)、自然哲学においても、西洋は決して東洋より高いレベルにあるものではありませんでした。
江戸時代にはいってまもなく鎖国となりました。そして、キリスト教や西洋思想を記述した漢籍(中国で出版された中国語で書かれた書物)も国内では禁書となりました。そして、朱子学が正式の官学となり、幕府お抱えの優秀な多くの学者(新井白石や室鳩巣などが有名です)が活躍し、幕末に至るまで基本的な教学とされました。
しかし、徳川吉宗の時代以降、西洋科学関係の書物が解禁となり、また蘭書(オランダ語の書物)の研究も推進されました。ここで、日本人の学者は、キリスト教の思想に触れない範囲で、西洋の科学を研究することができるようになりました。これが蘭学のはじめです。蘭学は江戸中期・18世紀中頃に興りましたが、江戸後期・19世紀前半になって、直接、蘭書から邦訳が作られることが多くなり、西洋科学思想に迫ることができる状況となりました。1854年の開国以降は、西洋の文化がどんどんはいってきました。西洋は、すでに産業革命を経験し、近代科学が革命的に発展を続けている時代になっていました。もはや、東洋と西洋の近代化のレベルの違いは歴然としていました。これ以降の日本の科学は、西洋科学の導入一辺倒になるので、ここでは扱いません。
本稿は、科学史や日本人の宇宙観についての議論を主眼としていませんので、このへんの説明はこれくらいにして、主眼である科学の「方法論」の話に戻りましょう。
5.日本の暦算天文学
さて、話を天文学に戻しましょう。ここで述べるのは、日本の江戸時代の天文学です。日本の天文学は、「天文現象の記録」と「暦算」をおもとしていました。前者は、天文観測をしてそれを記録・報告したもので、必要な場合は占いや予言をすることになっていました。日本では、実に多くの天象が記録され、その観測記録の数やレベルは17世紀以前の世界のトップレベルにありましたが、それによって天文学が発展するということはありませんでした。ただ記録するだけでは科学にはならないのです。彼らが、記録したのは、おもに「天変」的な珍しい不思議な天文現象であり、これを科学のレベルに持ってくることは、当時の天文学者の能力をはるかに超えたものでした。
一方、暦学は立派な科学でした。当時の暦は月の満ち欠けをベースにし、それを(太陽の位置で決まる)季節変化で補正した「太陰太陽暦」でしたので、太陽と月の視位置(天球上の座標)を精度よく計算することが最重要でした。暦というものは、少なくとも1年先までは必要なものですから、1年後の太陽と月の位置が計算で予測できないといけません。この計算の式を確定し、実際に計算して暦をつくり、そして観測と比較して必要ならば修正を施す(これを「改暦」という)のが、暦算天文学の主目的です。この暦算天文学の方法論が科学的であることは疑いないでしょう。しかし、この暦算天文学は、「現象論的」な法則を追求することに終始した「現象論的科学」の極致というべきものでした。それは、何らの「根本原理」も必要としなかったのです。
このように言うと意外に思われるかもしれませんが、暦算においては、(少なくとも江戸時代初期以前においては)、地動説も宇宙論も必要なかったのです。もちろん、万有引力の法則も必要ありません。それどころか、3次元幾何学も三角関数さえ必要ありませんでした。太陽と月の周期を用いて、その位置を出す「経験的な近似式」さえあればよかったのです。結果的に、太陽と月の天球上のおおよその位置が計算できれば、原理などはまたくどうでもよく、太陽が回っていようが地球が公転していようが、月の座標が三角関数になっていようが2次関数になっていようが、そんなことはお構いなしでした。(実際、驚くべきことに三角関数は、中国伝来の暦算天文学には含まれていませんでした。)計算結果が観測とよく合うかどうか、そこだけが焦点だったのです。これが暦算天文学の目的ですから、所詮そういうものでした。つまり、暦算天文学は、「現象論的法則」の精密化のみに主眼がおかれ、「根本法則」というものはどうでもよい、つまり、興味がないとされたのです。(第4図。根本法則は脇に置いてあります。)
暦算天文学は、江戸時代後期の麻田学派(民間の学者、麻田剛立(あさだ ごうりゅう)を師とする天文学者のグループ、弟子の高橋、間は幕府天文方となった)の優秀な学者によって、その極致まで発展し、のちに西洋の近代天文学を吸収・利用するレベルに達しましたが、その頂点に立つ高橋至時(たかはし よしとき)の思想には興味深いものがあります。かれは、自身において天体の運動を研究しておりながら、宇宙の根本原理というものについて言及するということはありませんでした。そして、暦算について、師の麻田が古代の観測と自身の計算とを一致させるのに苦心したことに触れ、「天文計算は今後も時代とともにだんだん精密になり、この学問はいつになっても完成することはないだろう。人の力で無窮の天を測ることなので、わずか千年、二千年の学問の集積で完成できるものではない。」という意味のことを書いています。
この高橋の言葉は、ニュートンとの大きな共通点と共に大きな相違点も示しています。彼は、ニュートンと同様、「根本原理」というものを忘れました。そして、自分たちの時代に行われた高精度の観測が、法則の正当化に何より重要であることを、十分認識していました。しかし、ニュートンは、少なくとも「より根本的な法則」により宇宙は記述できるということを信じていました。 一方、高橋は、この言葉を見る限り、「現象論的法則の高精度化」がすべてのように考えていたように思えます。これは彼特有の思想というものではなかったでしょう。暦算天文学はそういう哲学のものであったのです。精密な日本地図を作ったことで有名な伊能忠敬は、高橋の弟子でした(伊能の方が19歳も年上でしたが)。伊能がねばり強く正確な地図を作り続けられたことは、このような方法論の伝統にのっとっていることが大きいと私は思います。
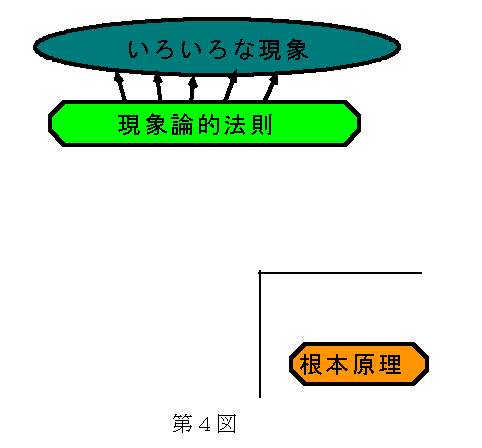
6.麻田学派、一歩を踏み出す
しかし、高橋の宇宙を見る目は、そこから一歩前進しようとしていました。彼は、恒星のそれぞれが、地動説における太陽のようにそれぞれの「太陽系」の中心に座っているという西洋の新説に触れ、「それならば歳差は恒星の運動に由来しているはずはなく、地球の自転と公転の間に由来しているのに違いない」という意味のことを主張しています。「歳差」は、天球上の春分点の移動のことを指すのですが、これは、現代では、地球の自転軸の向きが外の宇宙に対して変化することに起因することが知られています。この高橋の予想は正しいものでした。従来の暦算天文学の立場からすれば、「歳差」の理由などはどうでもよいことで(歳差の効果を知ることは非常に重要であるが)そんなことを考えることもなかったのですが、彼は、ちゃんとそれを「宇宙の幾何学」のなかで位置づけようと考えていたのです。かれは、やはり「より根元的なもの」として、「宇宙の幾何学構造」というものがあることは認識していたといえます。(第5図)
高橋の同僚である間重富(はざま しげとみ)は、画期的な考えを述べました。師の麻田剛立が提示したケプラーの第3法則(惑星の軌道半径の3乗と公転周期の2乗の比が一定であるという法則。高橋と間は、麻田がこれを独自に発見したと主張する)の理由として、振り子の周期と天秤の釣り合い(力のモーメント)のアナロジーを引き合いに出しました。麻田学派の人々は、この説明を絶賛したと言います。この間の説明が正しいかどうかはここでは問題ではありません。間は、少なくとも地上の法則で天体の運動を説明しようと試みたのです。現象論的法則に過ぎなかった「麻田剛立の法則(ケプラーの第3法則)」と振り子や天秤の法則との間には、共通の根元となる法則がある、ということを思いついたことは、かれらが、ニュートンと同じ道をたどる可能性を秘めていたことを意味します。しかし、それは、彼らの学問の本流ではありませんでした。
高橋の息子の代になって、幕府の天文学者は、西洋のニュートンの科学を(少なくとも表面的には)理解できるようになりました。彼らは、最初は「ケプラー運動」の暦算への導入からスタートしたのですが、最終的には、おそらく、ニュートンの打ち出した「より根元的な法則」というものを理解することができたと思われます。この部分は、彼らの思想には全く欠けていたものでしたから、それと相克するものは何もなく、案外すんなりと頭に入れることが可能になったものと思われます。
日本の暦算天文学は、「根本原理」どころか「より根本的な法則」すら必要としないものでした。しかし、西洋の天文学が「より根本的な法則」な法則を教えてくれたとき、おそらく彼らは大いに感銘を受け、その革命的な考えを個人的に受け入れたものと思われます。その感銘は、暦を作る上では表向きの影響を与えるものではありませんでしたが、彼らが、心の奥で長年待ちわびていたものだったに違いありません。
今回は、プロの暦算学者について書きました。次回は、やはり江戸時代の民間の学者による自然哲学の思想の発展について書きます。
(つづく)