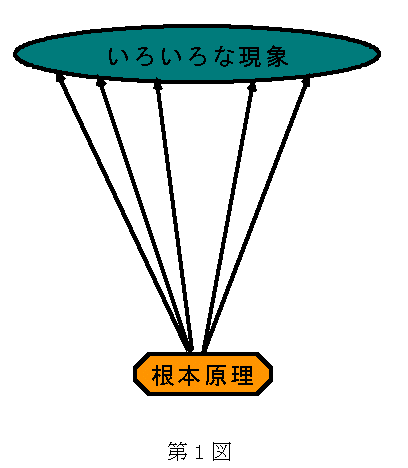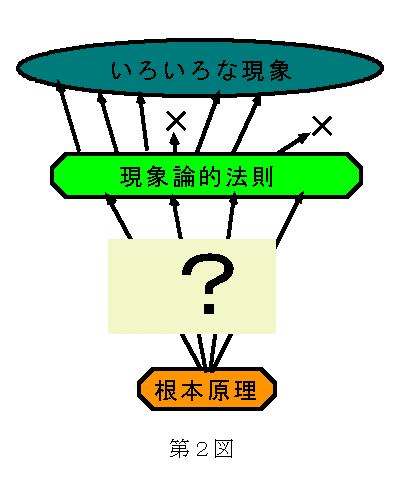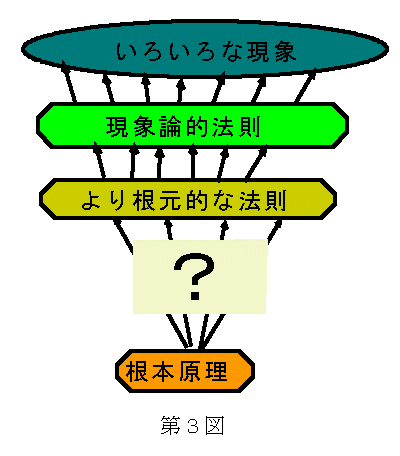西洋の科学、東洋の科学と日本の科学(第1回)
上原 貞治
0. 序
わけのわからぬ題名をつけてしまいました。ここで私は、現在私たちが「自然科学」と称して自然の真実の姿に迫ろうとしている方法は、決して唯一無二のものではなく西洋の近代科学として比較的最近発達したものであること、そして、東洋とくに日本には、歴史的には別のアプローチがあったことを、天文学史を引き合いにして書きたいと思います。2〜3回の連載としたいと思います。
この世の中にはいろいろなものがあります。天文、気象、大地、山川、海洋、動植物などの自然現象、身体、病気、誕生と死、精神、心理、感情、倫理などの人間に関する現象、政治、経済、産業、言語、道徳など人間社会に関する現象など様々です。数学や音楽などのような抽象的な学問・芸術もたいそう魅力のあるものです。このような多くの事柄を、総括的に理解することを目的として、科学や哲学、宗教というものが発生したことに異論はないでしょう。いずれも、人間の真実へのアプローチの方法と考えられます。
そのなかでも、科学の目的というのははっきりとしています。いろいろな種類の現象を比較的少数の「法則」で説明できたとしたら、いろいろな便利なことがあります。科学はこれをめざしているのです。まず第1に、多くのややこしい現象を頭の中で整理できますから、たいへん安心できます。第2に、良くできた法則の場合には、将来どういう現象が起こるのか「予言」ができます。(ここでいう予言は、「予報」という程度の意味で、超能力的な意味は含まないものとします。)第3に、法則を知った時、なんとなく自然の奥義に触れたような気がして、「私もえらくなった(あるいは神に近づけた)」という満足感が得られます。
1. 洋の東西の自然哲学
上に書いたような、人間の感情は、洋の東西を問わないものですから、この段階までは、西洋も東洋も同じであったと思われます。そして、自然哲学というものが誕生しました。自然哲学の一般的な手法は、まず、「自然の根本原理」というものを発見します。古代においては、これを実験的、または数学的に発見することは不可能であったので、直感あるいはそれほど厳密でない論理によってこれを発見しました。西洋の自然哲学のもととなった古代ギリシアの自然哲学では、自然の根本は「元素」であると考えました。アリストテレスは4つの元素を考えました。ピタゴラスは万物は「数」を基にしていると考えました。デモクリトスは、自然は分割不可能な粒子「原子」が組合わさってできていると考えました。これらは、ギリシアの人々が考えた根本原理です。学者によって具体的に元になっていると考えているものはかなり違いますが、いずれにしても、ごく少数の種類のモノが組合わさって複雑な世の中ができていると考えたことは共通しています。
一方、東洋の中国では、自然界のものは、「気」からできていると考えました。この「気」というのは、「気功術」とか「風水」とか、東洋の超自然的な占いや術で出てくる「気」のことですが、これはなにも抽象的、比喩的なものではなく、現実に存在するモノとして、当時の東洋の哲学者は考えていました。「気」はかなり広い概念を含むものなので、一言で説明することはできませんが、現代の言葉で言えば、気体(空気や化学物質の蒸気)、電磁場、波動、ひいては、人体から発生する場(オーラとかテレパシーのようなもの)まで含んでいると考えられます。とにかく、「気」というものが空間(物質の内部も含めて)に充満しながら流れており、固体や液体もこの「気」が固まってできたものと考えられていました。そして、この「気」の作用により複雑な現象が起こっていると考えたのです。東洋でも、木・火・土・金・水を元素と考える「五行説」というのがありましたが、これらは、「気」の下位にあるもので、いずれも気が具体的な形態をとったもの(中間状態)と考えられてました。中国の自然哲学は、「気」という目に見えない連続体が世界を支配していると考えたところに特色があります。
ここで大事なことは、ここでの自然哲学は、決して宗教あるいは占い、迷信といったものではなかったということです。これらは自然を虚心坦懐に見て考え出された説であったと見るべきだと思います。西洋と東洋の自然哲学の根本原理は、宗教や迷信とは明確に区別されるものなのです。なるほど、元素は「神が作りたもうた」ものと考えられたかもしれませんが、神がつくろうが自然にできようが、「自然は何々からできている」という探求には影響しないものです。 現在においても、多くのキリスト教やイスラム教の熱心な(原理主義的な)信者である科学者が、客観的な手法で自然の根本を解き明かそうと研究を続けており、宗教の教義と科学の目的が矛盾していないことは、このことを証明しています。また、中国の自然哲学からは、易とか儒教とかの占い・道徳に属する結果が導き出されましたが、これは、あくまでも「自然の根本原理」の「ひとつの解釈による利用」であって、「自然の根本原理」にさかのぼって影響を与えるものではありません。惑星の運動から人間の運勢を予言しよう、というのは占星術ですが、惑星そのものはどう見ても客観的に自然にあるものですし、惑星の運動そのものを観測したり予言したりするレベルにおいては、これは客観的な観測・または天文学であって、占星術はその下位のレベルにある人間界への応用に過ぎません。
ですから、宗教や占いから科学が誕生したというのは間違いです。科学も宗教も迷信も自然哲学を含む哲学から方法論の違いによって誕生したのです。次の章で、自然哲学がどのようにして科学に近づいていったのかを書きます。
2.科学の誕生
日常の生活を送ることはたいへんです。衣食住を確保し、隣人や友人とうまくつきあい、社会の秩序を維持し、病気や怪我をできるだけしないようにしないといけません。また、これらをことを子孫に引き継がせるための教育も重要です。
これらの重要な仕事をするために、いちいち自然哲学を持ち出して「自然の根本原理」にさかのぼり、具体的事象に演繹して考えていたのでは面倒でしかたがありませんし、そもそもほとんどの人々にはそこまで頭がまわらなかったでしょう。また、仮にこの方向で一生懸命考えたところで、正しい答えが出てこなかったことは明白です。たとえば、「明日の天気はどうなるか」というのは、生活の上でたいへん重要なことです。しかし、天気の予想をする際に、「そもそも空気は何々の元素からできており、雨は水であって...」というところから考えて結論を出すことは面倒ですし、これで実用的な予報ができるわけがありません。それより、「夕焼けは晴れ、朝焼けは雨」とか、「猫が顔を洗うと雨」とかという経験的な法則に従う方がはるかに的中確率が上がります。また、夕焼けの有無や猫というものは、深遠な知識がなくとも簡単に識別できますから、利用も簡単です。
でも、「夕焼けは晴れ、朝焼けは雨」という予報が偶然以上の確率で実際に的中するならば、それは決して迷信でもなければ、下等な俗説でもありません。何らかの科学的根拠のある一種の法則であることに間違いありません。このような具体的な事象と密接に関係した法則のことを「現象論的法則」と呼びましょう。「現象の上面(うわつら)のみを捕らえて、根本原理にまで言及していない法則」という意味です。注意しておきますが、この表現は、あとで述べるように階層の違いを意味したもので、「愚かな」とか「ばかげた」とか言う意味は全く含んでいません。
ですから、多くの人々にとっての「科学」は、こちら側(現象論的法則)からスタートしたものと思われます。生活の必要上、科学とか哲学とかを意識せず、実用やむなきのために考え出されたものといえるでしょう。
この状況を図にまとめると第1図、第2図のようになります。いずれの図も、一番下が、自然の根底にある「根本原理」、いちばん上が我々の目に触れる「具体的諸現象」となっています。第1図は、自然哲学の最終的な目標を表しますが、中間の矢印の部分については、古代の自然哲学者は具体的なことを知りません。第2図は、現象論的法則の適用について表したものですが、現象論的法則は100%の予言能力を持たないので、時々は正しい結論に至らないこともある(猫が顔を洗っても雨が降らないこともよくある)を示しています。ここは重要な点です。これは、第1図の根本原理が常に正しい予言を与えるであろうことと対照をなしています。たった1件でも間違った結論を導き出すとしたら、それは原理の欠陥であり「根本原理」の名に値するものではありません。一方、現象論的法則には、完璧な的中率は要求されません。「猫が顔を洗うとすぐに100%雨が降る」などとはそもそも誰も信じていません。(もしそうなら猫も気軽に顔を洗えない)。まあ、7割くらい当たれば上出来だと考えるのが常識的なところでしょう。7割当たれば「現象論的法則」としては十分に価値はあり、3割はずれたからと言って、それが法則の座を追われることはないのです。
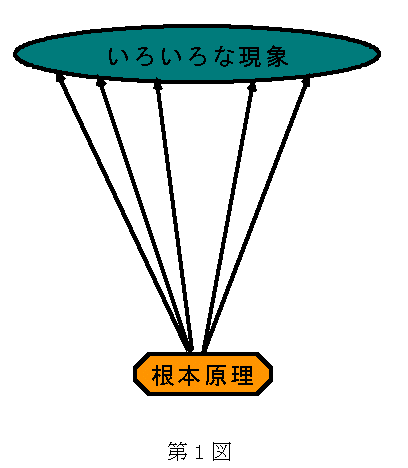
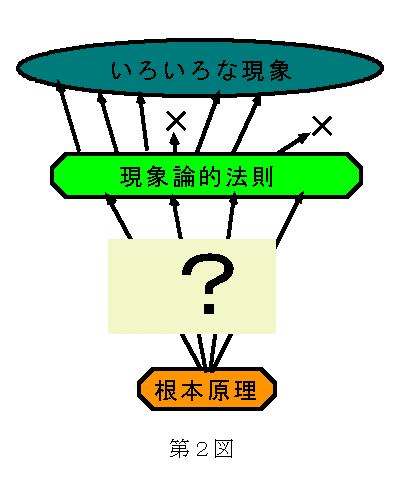
でも、「自然哲学」も「現象論的法則」もそれのみでは、科学とは言えません。この2つを何とか矢印で結びつけようとする努力を始めるところから科学の歴史が始まったものと私は考えます(第2図の?の部分をつなぐ)。天文学で言えば、1カ月の周期で月が満ち欠けし、1年の周期で太陽の南中光度が変わり見える星座が変化し、惑星が星座の間をぬって動くことは、洋の東西を問わず、古くからわかっていましたし、「現象論的法則」として漠然と理解されていました。しかしながら、この段階では、それらは単なる「知識」であり「科学」ではないのです。「それらをより深いレベルで理解しようとつとめること」から「科学」は始まったのです。また、「根本原理」と言っても、その正しさが実地で論理的に証明されない限り、ただのお題目あるいは個人の信念にすぎません。「論理的な証明」により、それは諸現象から接続されねばならなかったのです。
それには、2通りのアプローチの方法がありました。その一つは、「根本原理」→「現象論的法則」の方向から攻める方法であり、もう一つはその逆方向「現象論的法則」→「根本原理」の方向で解き明かしていく方法でした。
3.西洋の近代科学の発生
西洋における科学思想は、キリスト教的世界観を土台とし、それに多少の実証主義を添えることによって、スタートしました。そういう意味で、西洋の近代科学における根本原理は、キリスト教の「神の摂理」であるはずです。少なくとも、宇宙論においては、根本原理は、キリスト教的世界観と矛盾するものであってはなりませんでした。
一方、現象論的法則は、経験によって実証されるべきものと考えられました。しかし、実証のためには「客観的な実験」が必要だということが認識されたのはそう遠い昔のことではありません。比較的近代に至るまで、「根本原理」の知識が、客観的な実験の妨げになっていました。この困難な事態は、「イドラ論」を唱えたフランシス・ベーコンや、自ら実験を行い「新科学対話」で古い科学と新しい科学を対決させたガリレオ・ガリレイなどの16世紀から17世紀にかけた先駆的頭脳により、白日のもとにさらされました。
しかし、ここでは話を一足飛びにアイザック・ニュートンまでとばしましょう。ニュートンには、「私は仮説をつくらない」という有名な言葉があります。この言葉の意味するところは、ニュートンは科学の理論の仮説をつくらなかったと言うことではありません。もし、本当に仮説をつくらないのであれば、万有引力の存在を着想したあと、これを計算し、実際の現象と比較して証明することなどできなかったはずです。彼のこの言葉は、「私は、『根本原理→現象論的法則』という道筋を放棄する。」という意味なのです。彼は、根本原理の存在を(すくなくとも一時的に)忘れることを決心したのです。
運動の法則や万有引力の法則は「根本原理」ではないのでしょうか? 確かにそれらは現象論的な法則ではありません。ほとんどすべての物体の現象に適用できるし、基本的には(理想化された実験条件では)ほぼ100%正しい予言能力を持っています。しかし、ニュートンは、なぜ、このような法則が成り立つのかは説明できませんでした。彼は、それがなぜ成り立つのか、の問題については、上に書いたように「棚上げ」していたのです。ですから、この「新しい法則」を根本原理と呼ぶことはできません。ニュートンは、根本原理と現象論的法則のあいだに「中間的な原理」あるいは「より根元的な法則」というものを設置したのです。第3図を見て下さい。
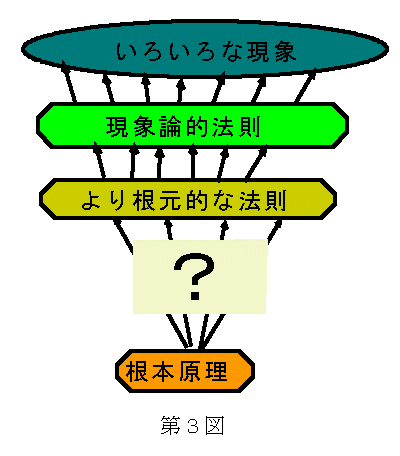
「より根元的な」というのは、比較において意味のあることばです。落体の法則というのがあります。ガリレイが、鉄の球を落下させて、落下距離は落下時間の2乗に比例することを見つけたとき、これは現象論的法則でした。しかし、彼が鉄の球も鉛の球も銅の球もみな同じ法則に従うことを見つけたとき、これは「より根元的な法則」なったのです。しかし、落体の法則は、運動の法則と万有引力の法則という「さらに根元的から法則」から導き出すことができます。こうして、ニュートンは、「現象論的法則→より根元的な法則→さらに根元的な法則→・・・・」と進むことによって科学は深まってゆく、ということを実際に示したのでした。その先に、「・・・→根本原理」がつながっていることを彼は理解していました。そして、それがはるかなる道のりであることも理解していました。ニュートンは有名な言葉を残しています。「私は、浜辺で貝殻を拾っている子供のようなものだ。時々美しい貝殻を見つけることはあるが目の前には大海が広がっている。」 ニュートンははるか遠くを見据えていました。そして、かれの万有引力の法則は、アインシュタインの一般相対性理論によって、時空間とエネルギーの作用という「さらにさらに根元的な」言葉により説明可能なものとなったのです。
次回は、日本の江戸時代に行われた東洋の自然哲学、天文学について書く予定です。
(つづく)