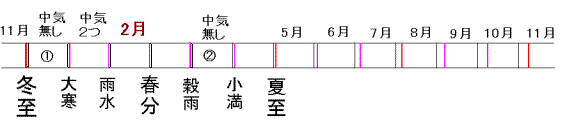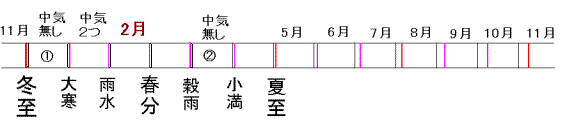旧暦入門(第3回)
上原 貞治
前回、日本の「旧暦」を含む東洋(古代中国起源)の太陰太陽暦の暦法の基本部分を紹介しました。それは、(1)新月を各月の1日とする (2)冬至のある月を11月とする (※)(3) ある年の11月から翌年の11月の間に中12カ月がある場合があり、その場合はいずれかの月を閏月とする。ということでした。そして、この閏月の入れ方こそ、「旧暦」のルールのもっとも複雑な部分です。このルールには「置閏法」という立派な名前までついています。この置閏法の説明が連載第3回めにまで持ち越されてしまったのは極めて遺憾で、今回は、無駄口をたたかずに一挙に閏月の入れ方に進みましょう。
(※)前回、一部に不正確なことを書きました。冬至と新月が同じ日に起これば、その日は11月1日ですが、その場合、冬至の瞬間と新月の瞬間の順序は問題ではありません。
9.「二十四節気」と「中気」
ところで、ひとつだけ無駄口をたたかせてください(あ〜あ)。「閏月」の読みですが、これは「うるうづき」と読んでも「じゅんげつ」と読んでも正しいです。でも、私の趣味から言うと、できれば「じゅんげつ」と読んで下さい。漢字で書いてある暦学用語のほとんどは中国語起源ですから、音読みが適当でしょう。「閏4月」は「うるうしがつ」でも「じゅんしがつ」でもどちらでもいいです。無駄口は終わり。
閏月の入れ方の説明には、二十四節気の説明が必要です。二十四節気の説明をまじめに始めるとそれだけで連載の1回を費やしてしまいますので、それは避けて、ごく簡単にいきます。二十四節気は冬至の兄弟のようなものだと思って下さい。冬至から次の冬至までの1年を24分割します。そして、その境界に次のような名前をつけます。冬至も二十四節気の一つです。ここでは便宜上、冬至を先頭とします(一般には立春を先頭にする場合が多いですが、暦学では冬至が起点です)。
冬至、小寒、大寒、立春、雨水、啓蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小満、芒種、
夏至、小暑、大暑、立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪
大雪(「たいせつ」と読みます)の次はまた冬至です。漢字二文字ばかりで憶えにくそうですが、冬至、春分、夏至、秋分(二至二分)の間のど真ん中に立春、立夏、立秋、立冬がはいり、その8つの隙間のそれぞれに、小寒・大寒(寒〜い)、雨水・啓蟄(雪が雨になって虫が出て来る)、清明・穀雨(春の天気は変わりやすい)、小満・芒種(麦を収穫、稲を植える)、小暑・大暑(暑〜い)、処暑・白露(ちょっと涼しい)、寒露・霜降(露が霜になる)、小雪・大雪(雪が降ってきた〜♪)のペアを入れるわけです。意外とシステマティックにできていますね。
さて、1年の24等分ですが、これには2種の方法があって、「時間均等法」と「角度均等法」があります。本当は、前者を「平気」、後者を「定気」と呼ぶのですが、「へいき」、「ていき」では発音も語感も似ていてわかりにくいので、ここでは、「時間均等法」と「角度均等法」でいきます。他の文献と照合する時は、「時間均等法」≡「平気」、「角度均等法」≡「定気」だと思って下さい。
「時間均等法」は簡単です。冬至から冬至までの1太陽年を24等分するのです。冬至は瞬間的現象ですから、時分の単位まで等分して下さい。1太陽年を365.2422日とすると、二十四節気の間隔は、365.2422÷12=15.2184日ほどになります。これで、各二十四節気の瞬間の日時を計算して決めます。
では、「角度均等法」とはなんぞや、ということになりますが、これは、地球の周りの太陽の周回運動(これでは「天動説」的説明ですが、太陽と地球の2天体だけを考えるなら、どちらがどちらの回りを回るのでも同じです)を念頭に置いて、太陽の1周回を24等分することになります。つまり、太陽が冬至から冬至まででぐるっと1回転すると考えて、この360度ぶんを24等分して、15度回ると二十四節気がひとつ進むと定義します。冬至から小寒までが太陽の15度の回転、小寒から大寒までも太陽の15度の回転、以下同様、と考えて下さい。あとで説明しますが、太陽の回りの地球の軌道が楕円形であることから、太陽の回転速度は季節ごとにわずかながら変化し、「角度均等法」では時間は均等になりません。動きが遅いところは、そこは同じ角度でも時間がかかることになります。「角度均等法」においては、太陽がその角度のところまで来た瞬間が該当する二十四節気ですから、経過した時間には直接の関係はありません。特急電車に例えると、運行時間を基準にするか通過駅を通過した時刻を基準にするかの違いです。
実は、現代の旧暦は、「角度均等法」を使っているのですが、説明の順序としてまずは「時間均等法」から説明します。閏月の入れ方としては時間均等法のほうが格段にスッキリとしています。
二十四節気の説明が終わったので、次に「中気」の説明をします。中気と言っても脳卒中のことではありません。各月の真ん中という意味です。冬至から始めて、二十四節気を一つおきに選んで12個をあつめますと、それら一つ一つが中気です。すなわち、中気は12あって、
冬至、大寒、雨水、春分、穀雨、小満、夏至、大暑、処暑、秋分、霜降、小雪
です。中気と中気の間隔は、「時間均等法」では、一律 365.2422÷12=30.437日くらいです。おおざっぱには、1カ月に1回、中気があるということです。
10.「時間均等法」(平気)による閏月決定法
江戸時代以前の日本では太陰太陽暦を使っていたのですが、天保15年(1844年)の天保の改暦以前は、「時間均等法」で閏月を決めていました。少し古い方式ですが、こちらの方式のほうがわかりやすく優れていると思うので、こちらから説明します。ここから、あとに書くことは、太陰太陽暦の細かい種類(暦法)によって違うことだと思って下さい。
冬至のある11月から翌年の11月までの間に中12カ月があるとします。この場合、どれかの月が閏月になります。次に中気を考えます。冬至と冬至の間には11の中気があります。つまり、12カ月あるところに11しか中気がありませんから、最低1つは中気を含まない月が生じます。その月を閏月とします。
つまり、箱が12個あって、豆が11個あり、すべての豆をどれかの箱に入れるわけです。豆がはいらない空っぽのままの箱が最低1つは残ります。
では、中気の入らない月は1つだけしかないのでしょうか? はい、この場合は1つしかありません。中気から次の中気までの間隔は30.437日くらいです。いっぽう、太陰太陽暦のひと月の長さは、29日か30日に決まっていますので、最大でも30日です。30.437日離れた2つの中気が最長でも30.000日の長さの区間に入るはずがありません。従って、2つの中気は1つの月には入りません。よって、中気の入らない月は1つだけです。なぜならば、箱が12個あって、豆が11個あり、すべての豆をどれかの箱に入れるわけです。でも、1つの箱に豆を2つ以上入れられません。豆がはいらない空っぽの箱は1つだけですね。これで、十分に数学的な証明でしょう。(証明終q.e.d.)
この「時間均等法」はそれなりに合理的ですっきりした規則と言えます。冬至を含む月が11月、大寒を含む月が12月、雨水を含む月が1月、...大雪を含む月が10月、そして、中気を何も含まない月が閏月です。単に「閏月」と呼ぶだけでは季節がわかりにくいので、その前の月の名を借りて、4月の次に閏月があれば閏4月、10月の次に閏月があれば閏10月と呼びます。
11.「角度均等法」(定気)による閏月決定法
ところがです。天保15年以降、日本の太陰太陽暦は「天保暦」になり、時間均等法を捨てて角度均等法にスイッチしてしまいました。そして、現代の旧暦は、この天保暦の置閏法を踏襲しています。従って、上の議論の前半(豆より箱が多い)は維持されますが、後半(1箱2豆禁止条項)はチャラです。チャラになってからすでに160年以上経ってしまいました。
なぜチャラになったと言えるか、それは、中気から中気までの長さが不均一で、30日以下になることがあるからです。「角度均等法」では、中気と中気の間隔は、時間ではなく、30度の回転が基準になります。これは、地球の軌道が楕円形で、太陽に近いところは速く回り遠いところは遅く回るからです。なお、地球と太陽がいちばん近づくのは現代では1月4日頃です(江戸時代とは多少変わっています)。「えっ、冬なのに、...」と思うあなた、北半球の冬は南半球の夏ですよ...
惑星の楕円運動(ケプラーの法則)は重要ですが、ここではあっさり割愛します。「角度均等法」による中気と次の中気の間の日数だけをリストしましょう。これは、今年(2010年12月〜2011年)のデータから取りました。次の表に限り、日付は現行の太陽暦によるものです。太陽暦での日付は年によって1日くらいずれますが、中気と中気の間の日数は毎年ほとんど変わりません。
冬至 12/22 08:38
大寒 1/20 19:19 冬至〜大寒 29.445日
雨水 2/19 9:25 大寒〜雨水 29.588日
春分 3/21 8:21 雨水〜春分 29.956日
穀雨 4/20 19:17 春分〜穀雨 30.456日
小満 5/21 18:21 穀雨〜小満 30.961日
夏至 6/22 2:16 小満〜夏至 31.330日
大暑 7/23 13:12 夏至〜大暑 31.456日
処暑 8/23 20:21 大暑〜処暑 31.298日
秋分 9/23 18:05 処暑〜秋分 30.906日
霜降 10/24 3:30 秋分〜霜降 30.392日
小雪 11/23 1:08 霜降〜小雪 29.901日
冬至 12/22 14:30 小雪〜冬至 29.557日
はい。ことの重大性は明らかになったと思います。中気の間隔が30日未満のところがありますね。天保暦、そして、「旧暦」のひと月には中気が2つはいることがありえるのです。ということは、1年に中気のない月が2つ以上生じることがありえるのです。でも、早合点してはいけません。閏月が1年に2つになるわけではありません。余分の月はあくまでも1つだけです。余分でない月まで閏月にすると、普通のナンバーが付く月に「欠番」が生じてしまいます。閏月はあくまでも1年に最大1つです。つまり、中気のない月が2つ現れると、どちらが閏月かを決定できなくなるのです。
たとえば、適当に状況を仮定して、何が起こるか見てみましょう。冬至が仮に旧暦の11月30日だったとしましょう。すると、次の月が小の月で29日しかなかったら、この月は中気がないかもしれません。冬至〜大寒は、29.4日くらいだからです。仮にそのように11月の翌月が中気無しだったとしましょう。その場合は、大寒はその次の月の1日になるでしょう。その月が今度は大の月なら雨水が同じ月の30日になることもあり得ます。2カ月で中気は2回消化されましたが、その中気がいっぽうの月に集中してしまいました。(図2の左から2番目と3番目の月を見て下さい)
さて、冬至が11月30日であるならば、次の冬至はその365日後あるいは366日後ですから次の年の11月10日ごろになるのでしょう。11月30日と次の11月1日のあいだの間隔は355日くらいになりそうですから、この間にすっぽり12カ月が入ることは必至です。その間の最初の2カ月で中気は2つ消化されました。ということは、残り10カ月で中気の残が9ですから、中気のない月が最低もういちど必ず現れます。上の表を見ると、春分以降に30日を大きく超える間隔がぽっかり開いて中気のない月を作ってやろうと待ちかまえています。この時、閏月は、11月の翌月でしょうか。それとも、春分よりあとの中気無しの月になるのでしょうか。(図2の①でしょうか? ②でしょうか?)
図2:中気無しの月(①と②)が1年以内に2度起こる例。黒線は月の境界、赤とピンクの線は中気。黒の月名は元々のルールで自然に決まる月の名前(一部省略)。追加ルールによると、春分のある月が2月になり、①が12月、②が閏3月となる。
さて、中気が入らない年が年に2回現れた場合、すでに出たルールだけでは、どちらを閏月にするかは決定できません。それで、追加のルールを置きます。それは、
・春分のある月は2月、夏至のある月は5月、秋分のある月は8月とする。
・閏月は中気のない月から選ぶ(でも、すべての中気のない月が閏月になるわけではない)。
というルールです。もちろん、冬至がある月は11月です。閏月でない月に「欠番」があってはいけない(「今年は『3月』がない」などというのは許されない)のも当然の了解とします。これらは「時間均等法」で満たされているルールと同じですが、どうして、これらが追加ルールになったのでしょうか。それは、これらのルールは、「時間均等法」ではわざわざ要求するまでもなく自動的に満たされる「法則」なのですが、「角度均等法」では同じ月に中気が2つ入ることが起こりうるために、改めて「規則」として要求してやる必要が生じたということです。つまり、これらが困った時の優先事項になるのです。
雨水と春分が同じ月になっても、その月は1月ではなく2月とします。上の図のように、冬至のある11月があり、次の月には中気が無し、その次の月には大寒と雨水の両方が入り、次の月に春分が入ったとしましょう。すると、春分の月が2月ですから、大寒と雨水の月を1月、その前の中気のない月①を閏月としますと、12月が欠番になってしまいますので、これは許されない。つまり、①の月が12月となります。この決定は譲れません。従って、本当の閏月はもっとあと、図では3月の次の②=閏3月、となります。
とまあ、こういう具合にうまくいきます。本当にどんな場合でもうまくいくのか? と心配する人がいるでしょう。あなたの勘は鋭い。実はうまくいかないことがありうるのです。世の中そんなに甘くありません。「失敗する可能性のある時は、いずれ必ず失敗する」(マーフィの法則)。反例があるのですから、肯定的証明はできません。反例は次回に紹介することにします。
天保の改暦以後、この太陰太陽暦が日本国の公式の暦であったのは明治5年までのわずか29年間にすぎませんでした。その間にこの「角度均等法」による閏月の決定がボロを出すことはありませんでした。その間に閏月はわずか10回しかなく、追加ルールで事なきを得ました。しかし、不幸なことに同じ方式が「旧暦」に引き継がれました。もはや旧暦は正式の暦ではないのでボロを出しても社会問題にはならないのですが、今後、いまさらながらに欠陥を露呈するということにはなるのです。暦学においてはマーフィの法則は真理です。
12.若干の疑問に答える
Q.なぜ時間均等法をやめて、角度均等法を採用したのですか。
A.なぜこんな不具合の出る可能性のある角度均等法を採用したか、というご質問でしょうが、 それは、時間均等法にも欠陥があって、春分と秋分が本当の春分、秋分にならないからだと思われます。本当の春分、秋分とは太陽が天の赤道上に来る瞬間です。時間均等法で計算しますと、現在の太陽暦で2011年の春分は、冬至の91日後ですから、3月23日になってしまいます。2日もずれてしまいます。秋分は、次の冬至の91日前ですから9月22日となります。これも1日ずれます。天保暦が設定されたのと同時代の中国ではすでに角度均等法が使われていましたし、西洋の天文学でも正しく角度に従って春分、秋分を決めていました。日本だけずれた日付の春分、秋分を公言することは恥だとされたのでしょう。
Q.中気のない月を閏月にするという規則の根拠は何ですか。
A. この質問には簡単に答えられます。時間均等法では、ナンバー付きの各月に中気が1つづつで、月のナンバーと中気は1対1に対応します(10節の終わりのあたりで説明しました)。中気は太陽が基準なので季節に直接対応しますから、季節と暦の日付が±15日以上ずれることは起こりません。新月を1日にするという太陰暦を維持しつつ季節とのずれを最小限にするという知恵だったのです。各月の中気が月のナンバーと対応し、いずれハシタがたまってきて中気がない月が現れます。このときに、季節とのずれを調整するために月のナンバーの進行を一旦ストップする、という意味で閏月をここに入れたのでした。
角度均等法で、ナンバー月に決まった中気が対応するという原則は一部崩れましたが、追加ルールによって3カ月に1度の対応は維持され、時間均等法に準ずる程度の季節のずれに収めようとする努力が認められます。
以上2点において、もちろん、角度均等法への批判は大いにありますが、これは現代の旧暦への批判ということにもなりますので、それは次回以降に議論したいと思います。
おまけ(資料紹介)
旧暦(あるいは昔の日本の太陰太陽暦)を自分で計算して決めたり、日付と季節との関係を検討しようとすれば、複雑になることが骨身にしみるほどわかっていただいたと思います。しかし、ある1年の日付をただ知るだけなら簡単です。閏月の有無、あるいは何月が閏月か、と毎月の大小(30日か29日か)の情報さえ得ればいいからです。たとえば、1月〜12月までの月の大小をリストして、閏月があればカッコに入れて挿入することにすれば、「大小大大小大(小)小大小大小小」などと表現できます。これだけで1年分の日付(この例では383日ぶん)が完全に表現できることはご理解いただけるでしょう。やっかいなのは、これが毎年不規則に変わることで、過去については表にして記録保管しておかないといけませんし、新年ごとに新しい暦を入手して、記憶するなり掲示しておく必要があります。でも、上の通り、せいぜいカッコを含めても15文字ですからたいした場所は食いません。憶えやすくはないですが、保存は簡単です。
歴史や天文暦学を研究する人用に、歴史年代の各年の月の大小を載せた本が出されていました。図3は『皇和通暦』という江戸時代に出た本の2ページぶんで、その鎌倉時代のあたりです。縦一行が一年分(1ページが10年分)で、上から1月、2月となっていて、横棒が大の月(「大」の字は横棒から書き始める)、縦棒が小の月(「小」の字は縦棒から、...よく考えてありますね)、一カ所に2つ並んで書かれているところは右から読んで左側が閏月です。たとえば、承久の乱があった承久三年(1221年)は「大大小小大小小大小大(小)大大」だったわけです。これで歴史の研究もバッチリですよね。なお、現代では、ネットにつながっているパソコンがあれば、Wikipediaの「承久」を見ればこんなことはすぐにわかりますから、『皇和通暦』を買わなくても大丈夫です。

図3:『皇和通暦・修訂版』より一部(日本科学技術古典籍資料 天文学篇3より)
(つづく)
今号表紙に戻る